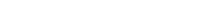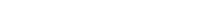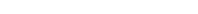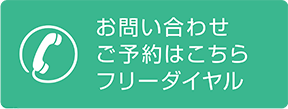福岡校基礎コース修了 柿木良子さん 38歳
大切なことも思い出せないくらい、がんじがらめになっていたあの頃の私
他人が嫌い。自分のことはもっと嫌い。それが過去の私だ。
私は人を憎むことに人生の大半を費やしていた。
そんな自分に気付いた時、私は自分自身を本当に哀れだと感じた。
きっかけは何であれ、そういう風に生きてきた自分がかわいそうで仕方なかった。ちょうどその頃、祖母が他界した。祖母はずっと私を守ってくれた人の一人であり、私を支えてくれた。私は九州の山奥の小さな町で生まれ育った。
近隣は祖父母の兄弟姉妹の代からの親族が住んでいる親密なコミュニティ。
わずらわしい部分もあるが、お互いに支えあうのが当たり前の恵まれた環境。
そんな中で、私はいわゆる「変わった子」だった。
「何で他の子と同じようにできないの?」「お前はおかしい。」と、よく両親に言われていた。
他と異なることを許さず、私を認めていない両親。
特に母とはうまくいかなかったが、そのことには諦めがつくようになった。
ただ、家ではいつも孤独だった。そんな私に祖母は言ってくれた。「昔と違って今は、男女関係なくいろんなことも出来るようになった。これだけ親戚がいるんだから、ちょっとくらい変わった人間がいてもいい。行きたいところに行っていいんだよ。勉強でも仕事でも、自分が好きなことを一生懸命やっていいんだよ。幸せの形はひとつだけじゃない。」最大の理解者であった祖母の死は、私に大きな喪失感を与えた。
祖母の死を悼むとともに、私自身に対し涙が止まらなかった。
大好きだった祖母が安心して旅立てるよう、私が私を幸せにしてあげようと誓った。私が自分自身を変えようと決意するきっかけを与えてくれた人が祖母の他にもう一人いる。
そのころ親しくしていた女性である。仮にAさんとしよう。
Aさんは私が通っていた美容院の美容師だった。
何度か担当してもらううちに意気投合。
二人ともお酒が好きということもあり、一緒に飲みに行ったり、互いの部屋を行き来したりと急速に仲良くなった。
私より7歳年上で波乱万丈の人生を送ってきたAさん。独立して自分の店を出すという夢を実現させたAさん。
たくましくパワフルで、頼りがいのある姉のような存在だった。
当たり前のことだが、付き合いが深まるうちにお互いの悪い面も見えてくる。
育った環境も価値観も異なるのだから仕方ない、それも彼女の個性だと私は思っていた。だが彼女は違った。
私に対し、完璧な友人としての役割を求めていたのかもしれない。
私の言動が彼女の意に沿わないこともある。
私とAさんの意見や感想が違うこともある。
Aさんからの誘いを断る日もある。
そういったことでも、彼女には許せなかったようだ。「私がどんなに傷ついたか、わかる?」
「私はあなたのためを思って誘ったのに、断るっておかしくない?」
「私はこう思うんだから、あなたも同じように感じて当然じゃない?」
「あなたが違う意見を言ったせいで、私はすごく不愉快なのがわかる?」
「私の話を聞いてほしいって言っているのに、すぐに来てくれないって思いやりがないよね?」
「もう飲んでるからって、言い訳するの? タクシー使えばすぐに駆けつけられるでしょ?」
「あなたのせいで、私は・・・・」
Aさんからすれば友人としての当然らしいが、私には私の生活があり、仕事があり、感情や価値観がある。しかし彼女の言い分はこうだった。
「だって、私たち親友でしょ?」
「親友だったら、私を助けてくれて当然でしょ?」
「どんな時でも来てくれる、それが親友でしょ?」
「私はあなたにこれだけのことをしてあげたのに、恩を仇で返すの?」自分の痛みには非常に敏感で、常に自分優先。
周囲は自分のために何かをしてくれて当然、悪いのは他人。
彼女の周りには友人や仲間が大勢いるように思っていたが、よく見ると、深く付き合ってる人はほとんどいなかった。
Aさんは表面的には元気で明るい人だったが、その反面自分は不幸だといつも嘆いていた。
いつも誰かを憎んでいた。誰かに依存したり、攻撃することで、幸せになろうともがいていた。ある日、ふと思った。
Aさんは私自身である。
彼女は私自身を映した「鏡」だ。
彼女が不幸なのは決して周囲のせいではない。
周囲の人は可能な限り彼女を助けた。
ただ、その気持ちは彼女に届かずにやがて周囲の人は距離を置く。
彼女自身が彼女を不幸にしている。私もまた、自分自身を不幸だと思っていた。
誰のせいでもない。無限にある選択肢の中から、自分を人を憎むことを選んだのは私自身だ。
許すことも選べたはずだ。人の優しさや愛情を受け入れることも選べたはずだ。
このままでいたくない。
私は私のために、幸せになりたい。
変わりたい。
憎しみから解放され、自由になりたい。
真っ暗な日々から抜け出したい。
心穏やかに生きたい。自分自身を振り返るのは、苦しくて辛い作業だった。
自分の傷を盾にして、どれだけ人の気持ちを踏みにじってきたのだろうか。
どれだけ人を傷つけてきたのだろうか。どうして自分だけが不幸だと信じ込んでいたのだろうか。
これが「私」。今までの「私」。祖母が他界し、離婚問題をかかえていたこともあり、毎晩のように吐いた。
体重が一気に落ちた。
自己否定と、当時の夫からの否定。
自分だけではどうにもできなくなり、カウンセリングに通った。「辛かったですね。よく今まで頑張ってきましたね。あなたが変わろうと決心したのなら、あなたは自分自身を変えていけますよ。」その一言で、救われた。少しずつだが、楽になっていく心と身体。
私が私自身を認めよう。長所も短所もすべて受け入れよう。
私の中の光も闇もすべてひっくるめて抱きしめよう。
今までたくさん憎んできたのだから、これからはたくさん愛していける。
私自身のことも周囲の人のことも。今まで出会った人たちの優しいことばを思い出した。
多くの人たちに支えられていることも思い出した。
こんなに大切なことも思い出せないくらい、がんじがらめになっていたのだと痛感した。
心が閉ざされているとはこういうことなのだと実感した。いつもと同じ景色のはずなのに、奇麗に見えてくる。視界がクリアになってくる。
思い出もあたたかく優しいものに変わっていく。
周囲も私自身も驚くほどに、私の表情が変わってきたころ、無事に離婚が成立した。
新生活のスタートを古くからの友人たちが祝ってくれた。
陰になり日なたになり、私を支え見守ってくれていた人たちだ。
素直にうれしいと思い、感謝の気持ちでいっぱいだった。
人に支えられてきた分、今度はお返ししていきたいと思った。
心理学や私を救ってくれたカウンセリングを勉強しよう。
そんな中、日本メンタルヘルス協会に出会えた。私にとって必然の出会いだったと思う。
祖母の死、Aさんとのしがらみ、離婚。
あの頃は辛いことが重なったけれど、これもすべて必然だったのだと今は思える。そして講座を受ける中で、両親との確執をそのままにしていたことに気づく。
なんの努力もせずに、自分から両親に歩み寄ろうともせずに、適度な距離をおいていた。
基礎コース後編の「本当の自分に出会える音楽力」のワークで両親の顔が浮かばなかったことに衝撃を受け私は泣いた。
そして、まだ幼かった甥のことばを思い出し、さらに泣いた。
当時、甥は三歳だった。結婚生活で子供が出来ない私に対し、母はいつものように言った。「まだ子供が出来ないの?あんたは、やっぱりおかしい。兄弟にも従兄にもみんな子供がいるのに。なんで、みんなと同じように出来んの?」私もいつものように適当に聞き流した。「そうね、きっと私がおかしいんだろうね。」その日、甥と二人で遊んでいるときに、彼は急に真剣な顔になり私に言った。
「あのね、『しゅうへい(甥の名前)』は、みんなの『しゅうへい』でしょ?
『りさ』もみんなの『りさ』だし、この前生まれた『ゆうか』もみんなの『ゆうか』。
それでね、『りょうこ姉ちゃん』は、ぼくたち、みーんなの『りょうこ姉ちゃん』なの。
ぼくたちが、ちゃんとここにいるからね。大丈夫だよ。心配しなくていいからね。『りょうこ姉ちゃん』は『りょうこ姉ちゃん』でいいんだからね。」
まだ三歳の甥の言葉で、私は私でいいのだと思えた。母は私を理解できない。
それは現実。
私も母を理解しようともせず、親子でもこんな関係もあるのだろうと諦めていた。
しかし、本当は誰よりも私のことを解かってほしかったのだ。
ありのままの私を受け入れて欲しかったのだ。
講座を通してやっとそのことに気付かされた。
母にも、私たちを育てていく中で、誰にも言えない辛いことや悲しいことがたくさんあったに違いない。
耐えて歯を食いしばって出てきた言葉は、私を傷つけたかったのではなく、不器用だっただけかもしれない。
母には理解者がいたのだろうか?母も、私に解って欲しかったのではないだろうか?
メンタルに出会わなければ、ずっと母との関係を諦めたままだったのかも知れない。現在勤務している会社が大量リストラを行い、私もあと数日でこの会社を去る。
これから、少し長い人生の夏休みに入る。
このタイミングで、この夏休み。
きっと、母とゆっくり過ごす時間をプレゼントされたのだと思う。
いつもより長く、故郷に滞在しよう。
母とたくさん話をしよう。
そして、あの日、祖母や甥が私に寄り添ってくれたように、今度は私が母に寄り添っていこう。